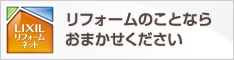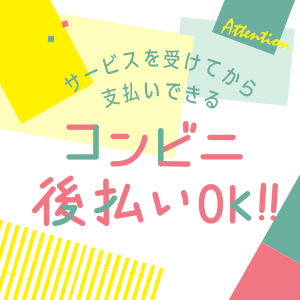水のコラム
出雲大社で感じる節分祭の風情|行事の魅力や季節の変わり目を迎えるコツをご紹介【水道職人:プロ】

立春を前に、冬から春へと移り変わるこの季節。
古くから「邪気を払い、福を招く」とされる節分には、豆まきや恵方巻きなど、心がほっこりする風習がたくさんありますよね。
そんな中、島根県出雲市の出雲大社では、厳かな雰囲気と深い歴史を感じられる「節分祭」が毎年行われています。
今回は、出雲大社の節分祭の由来や見どころを中心に、節分ならではの豆知識や、季節の変わり目にこそ気をつけたい暮らしのポイントまで、幅広くご紹介したいと思います。
出雲大社の節分祭とは

島根県出雲市にある出雲大社といえば、「縁結びの神様」として全国的に有名ですよね。
実は、この出雲大社で毎年行われる節分祭も、多くの人が心待ちにしている伝統行事のひとつなんです。
由来と歴史
「節分」という言葉には、「季節を分ける」という意味があります。
立春の前日にあたる節分には、豆まきなどを通して邪気をはらい、新しい季節を迎える準備をするという考え方が古くから伝わってきました。
そんな節分の行事が、出雲大社では「節分祭」として大切に受け継がれています。
大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)をまつる出雲大社は、縁結びだけでなく“国づくり”の神様としても知られています。
季節の変わり目に国中の平和や人々の健康を祈る行事は、歴史ある神社だからこその重みを感じますよね。
神話の舞台となった土地で行われる厳粛な行事に触れると、自然と新しい季節を迎える心構えが整うかもしれません。
節分祭の概要
出雲大社の節分祭は、毎年2月の節分の日に合わせて執り行われることが多いです。
年によって日程や内容に少し変化がありますが、一般的には下記のような流れで進みます。
・厳かな神事による祈願
宮司や神職が、参拝者の無病息災や厄除けを願いながら儀式を行います。
・豆まきと福豆の配布
「鬼は外、福は内」の掛け声とともに豆をまいたり、
縁起の良い福豆をいただくことができます。
・限定の御朱印やお札
節分祭限定の御朱印や、お守りなどが授与される年もあります。
コレクションしている方には見逃せないポイントの一つです。
春の訪れに向けて、心を整えるきっかけとして足を運んでみてはいかがでしょうか。
出雲大社の節分祭を楽しむポイント

せっかく出雲大社まで足を運ぶなら、節分祭の雰囲気を存分に満喫したいものです。
行事そのものだけでなく、境内の空気感や周辺の観光スポットなど、知っておくとより一層楽しめるポイントがいくつもあります。
見どころと参拝の楽しみ方
出雲大社の節分祭では、厳かな神事はもちろん、豆まきや福豆の授与にも注目です。
大勢の人でにぎわう場面では「鬼は外、福は内」のかけ声とともに豆がまかれ、参拝者たちが一斉に手を伸ばす光景はとても活気にあふれています。
運よく福豆を受け取れたら、その年の運気がさらにアップするような気分になれるかもしれません。
また、神事の合間には本殿や拝殿をじっくりと巡ってみるのも一興です。
空を仰ぐようにそびえる大しめ縄や、広々とした参道の景色を眺めるだけでも特別な気持ちになれます。
静かな時間を過ごすことで、厳粛な行事とにぎやかな豆まきの両方をバランスよく楽しめるはずです。
周辺にも楽しめるスポットが豊富
周辺観光としては、出雲大社正門前の神門通りにあるお土産屋や食事処巡りが定番のスポットとして人気です。
名物の出雲そばや焼き立てのおやき(和菓子)など、食べ歩きが楽しめるお店がたくさん並んでいるので、お腹も心も満たされるひとときが過ごせます。
さらに足を伸ばせば、稲佐(いなさ)の浜や日御碕(ひのみさき)灯台など、神話や自然を感じられる絶景スポットも豊富。
節分祭を堪能したあとは、ぜひこうした場所にも足を運んでみてください。
節分にまつわる豆知識

節分が近づくと、スーパーやコンビニの店先には豆や恵方巻きがずらりと並びます。
普段はあまり意識しないですが、ふと「どうして節分に豆をまくんだろう?」なんて気になったことはありませんか?
なぜ豆をまくの?豆まきの意味
「鬼は外、福は内」というおなじみの掛け声とともに豆をまく姿は、日本のお正月行事などと並んで広く知られています。
豆には「魔(ま)を滅(め)する」という語呂合わせのほか、穀物に宿る霊力で邪気を払うという考え方が古くからあったそうです。
豆をまくことで、自分や家族のまわりにある不運や悪い気を外へ追い出し、代わりに福を呼び込もうとするのが豆まきの目的と言われています。
もともと豆は、五穀豊穣を願う神事でも大切に扱われるものですので、そんな豆を使った節分行事は、今も昔も多くの人に愛され続けている日本の風物詩といえるでしょう。
恵方巻き・いわしなど縁起ものの紹介
節分といえば、もうひとつ欠かせないのが「恵方巻き」です。
もともとは関西地方を中心に広まった風習で、その年の恵方(神様がいるとされる縁起のいい方角)を向きながら太巻きを丸ごと一本、黙って食べることで福を逃さずに取り込むといわれています。
最近は具材もバラエティー豊かで、海鮮やカツ入りなど、お好みの味を選べるの楽しみの一つになっています。
また、節分には「いわしの頭を柊(ひいらぎ)の枝に刺して飾る」といった風習も知られています。
これは、においの強いいわしとトゲのある柊で鬼や悪いものを寄せ付けないという昔ながらの厄除け法だそうです。
地域によっては今も大切に受け継がれている風習で、こうした小さな行事の積み重ねが、日本ならではの季節感を感じさせてくれます。
節分祭の時期に意識したい暮らしの準備

立春を前にしたこの時期は、寒さが続くものの、少しずつ春の訪れを感じ始める節目でもあります。
気温の変化に合わせて体調を崩しやすい人も多いため、自分や家族の健康はもちろん、お家のコンディションにも気を配りたいところです。
ここでは、この時期の暮らしの準備について簡単に触れておきたいと思います。
季節の変わり目の体調管理
冬の冷たい空気から春の穏やかな気候へ移ろう時期は、昼と夜の気温差が大きくなりがちです。
寒いと思って厚着をしていたら、日中はポカポカ陽気で汗ばんでしまった…という経験をされた方も少なくないはず。
体温調節の難しい季節だからこそ、脱ぎ着しやすい服装がおすすめです。
また、風邪やインフルエンザ、コロナウィルスなどへの対策も欠かせません。
節分祭のような人が多く集まる行事に参加する際は、マスクやハンカチなどを常備しておくと安心です。
住まいの豆知識:水回りチェックのすすめ
体調だけでなく、家の中のコンディションも整えておくと、より快適に春を迎えられます。
特に気温差の影響を受けやすいのが、水道管や給湯器まわり。
徐々に気温も上がってくるこの時期ですが、寒さが厳しい地域ではまだまだ安心できません。
寒の戻りなど気温がグッと下がった日には、水道管が凍結してしまうなんてこともあるので、事前に保温材を巻く、夜間は少し水を流しておくなど、簡単な工夫をしておくと安心です。
また、排水口やトイレのチェックも大切です。
外気に触れやすい位置にある場合など、思わぬトラブルが発生してしまうこともよくあります。
もし凍結や破損などの症状を発見した場合は、早めに専門業者へ相談してみてください。
出雲大社の節分祭を満喫するために

ここまで、出雲大社の節分祭の魅力や豆知識、そして季節の変わり目を快適に過ごすためのちょっとした準備についてご紹介してきました。
節分は新しい季節を迎える大切な節目。
出雲大社の荘厳な雰囲気に触れることで、冬から春へと移ろう時の静けさと活気を同時に味わうことができます。
神事を見学したり、豆まきを体験したり、恵方巻きを食べたりと、日本ならではの行事を存分に楽しんでみてください。
水回りの困りごとは「しまね水道職人」へ
また季節の変わり目に際し、水道管の凍結や給湯器の不調など水回りのちょっとしたトラブルが起きた場合は、ぜひ私たち「しまね水道職人」にご相談ください。
急なトラブルから定期的な点検まで幅広く対応しています。
わかりやすいお見積りやご案内を徹底し、安心してご依頼いただける水回りのパートナーとなるべく、地域に根差したサービスを心掛けております。
修理のタイミングを逃すと、症状が悪化して余計に費用や手間がかかってしまう場合もありますので、早め早めの対処が大切です。
心配事を解消して、どうぞ安心して季節のイベントを楽しんでください。
関連記事


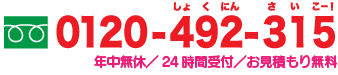

 洗面所の詰まりは要注意?危険な理由につい...
洗面所の詰まりは要注意?危険な理由につい...  トイレタンクの水が止まらない!原因と対応...
トイレタンクの水が止まらない!原因と対応...  シンク周りで起こるキッチンの水漏れトラブ...
シンク周りで起こるキッチンの水漏れトラブ...  早めにやっておきたい水道管の凍結防止対策...
早めにやっておきたい水道管の凍結防止対策...